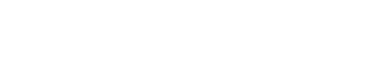blog
Writer/Maya 事務・CADオペレーター
「建築」や「モノづくり」の最前線に立ち、設計者の価値観に基づいた機能的及び情緒的な価値をお伝えできればと存じます。
「弥生の家」平均的な規模の玄関を広く見せる。
本日2投目は、引き続き「弥生の家」ツアーを。
いよいよ玄関を開けてみます。
適度に重量のある扉を開けると・・・


間口1,820mm、奥行き2,730mmの平均的な規模の玄関及び玄関ホールが広がっています。
広さを感じさせるには「跡部の薪ストーブの家」のように、玄関の幅を広く取るのが一番有効なのですが、
間取り上不可能な時は設計上の工夫が必要になってきます。


ここの家で言うと、余計な線のないシンプル構成・FIXやハイサイドからの採光・高さを抑えた下駄箱など。
出来るだけゆったりと見えるように専務の挑戦は続きます。
「弥生の家」造作オープンガレージ
岐阜という土地柄か生活の足となる自家用車に対しての意識は非常に高く「造作ガレージ」の話題はよく耳にします。
何らかの理由で不採用となっても、計画段階で皆さんが興味をもたれるキーワードの一つであり、
弊社としてもこれから先も力を入れたい事柄です。
そんな注目度の高い造作ガレージですが、「弥生の家」では、2台分の駐車スペースと外部収納を設けました。


過去の事例をみてもオープンタイプのガレージが多いですが、
車にアクセスしやすく通風・採光に優れ、コストも削減できるなどメリットが豊富だからです。
防犯を最優先するならばクローズタイプでしょうが、その敷地や使い勝手によりタイプを決めていきます。
そして、奥の黒い扉を開けると5帖の収納空間が。


内部は、出来るだけ安価な材料でコストカット。
作業台や棚を設えたりちょこっと工事で利便性を向上させることも可能です。

<富加の平屋の外部収納内>
通常、憧れ的存在の造作ガレージですが、毎回コストのバランスを整えながら造作しています。
もし、ガレージいいな~とお考えでしたら一度ご相談くださいね。
「弥生の家」竣工おめでとうございます。
「上川辺の家」に続きまして、本日から「弥生の家」の見所をご紹介していきたいと思います。
過去記事を遡ると上棟と外観イメージでストップしておりますので内容を濃ゆ~くしていきたいと思います。
まず、その外観から。

「自分らしい家」は、何かが周囲の家と異なると思いますが、
この家の場合、その何かとは、この前面に設けた「ガレージ」にあるのではないでしょうか。
計画当初からこのガレージ造りが念頭にあり、N様のカーライフの充実を願って外部収納付きのガレージを造作させていただきました。
長くなりそうなので、ガレージについては又後程。
そして、もう一つの特徴として、ガレージと居住エリアを連結させボリュームを操作していることが挙げられます。


ここからのアングルだと閉じた印象ですが、ガレージが光と風のトンネルとなり、居住エリアの環境を快適に保ちます。


観る角度によって印象がまるで違うのも自由設計の面白いところ。
最後に、居住エリア。


シャープな箱型フォルムにみえますが、1.5寸勾配の緩やかな片流れ屋根となっています。
端正なお顔立ちとキレの良い表情が、カッコイイ車好きのご一家にピッタリな気がします。
延床面積33.5坪の箱の中身は、どんな空間が広がっているのか。
次回、ご案内致しますね。
申し遅れましたが、N様竣工おめでとうございました!
工事関係者の皆様、丁寧なお仕事を本当にありがとうございました。
「喜多の家」外観イメージ
先日、上棟の様子を少しアップ致しました「喜多の家」。
全体像が全くわかりませんでしたし、本日は、外観イメージをお伝えしたいと思います。
その前に・・・
ここの土地の特徴ですが、まず第一に、出入り口の間口が狭く少々旗竿気味だったりします。

第二に、住宅が密集しているエリアですので、周囲が建て込んでいる。

「泉の家」と同様に「囲まれている感」を感じる敷地であり、採光や通風の面で工夫が必要となってきます。
又、採光・通風の他、プライバシー、駐車スペース、資材の運搬、と課題は山積み。
しかし、家の敷地となる部分は88坪あるので間取りの自由はききそうです。
しかも、周囲が開けた旗竿より既に周りに建物が建て込んでいる状態の方がイメージがしやすいのもメリットと言えます。
そこで、専務が導き出したのは、

旋回できる駐車スペースから玄関まで最短で素直な動線やハイサイドからの光の利用、適材適所に開けられた開口など
更地の時に感じた「囲まれている感」を感じさせない明るい家。
この敷地のデメリットをどう扱ってカタチになっていくのか。
長年の建築経験と知識と感性に期待です。
「鷹之巣の薪ストーブの家」祝!上棟。安全性と耐久性に優れる木造軸組工法
春風の心地良かった先週の金曜日、今月2棟目の建前が行われました。

現場に到着した正午過ぎには、すでに柱や梁が組み立てられ粗方のシルエットが浮かび上がっておりました。
この家は、基礎の段階で、通常と異なる造りだったわけですが、


躯体が現れたことにより、その用途が想像しやすくなったのではないでしょうか。
基礎周辺のコンクリートの立ち上がりと外部収納にしては広すぎるポーチと同レベルの土間コン。
仕上がりが、非常に楽しみな部位です。
応援大工さん、共に腕を振るう専務とその様子を伺う社長を激写。





近くで見ると、垂木をそのまま仕上げにする軒天井なのが分かりますね。
断片的ですが、和のエッセンスを感じ取ることが出来ます。
西より。

こっちから見るとコンパクト。
この広~い敷地だからこそできる家のカタチ。
プランを練りに練ってきた案なのでO様ご一家の笑顔が思い浮かんできます。
O様、上棟おめでとうございました!
これからは、現場での打ち合わせが増えますが宜しくお願い致します。
一日中頑張ってくださった大工の皆さん、レッカー作業員さん、本当にありがとうございました。
「加茂野の家」コテ塗り

現場は、コテによる外壁塗装が完了しております。
「小山の家」と同様に、ジョイント目地を消して意匠を高めています。
別アングルから。

この仕上げによって和の風情が格段に上がったのですが、色味が上手く撮れません(苦笑)
アップで。

質感はこの通りですが、色味はこちらも全然違います(苦笑)
とても落ち着いた良いお色目ですし晴れの日にリベンジしてきます。
「小山の家」現場の様子
先週、下地のジョイント部分を消す目地消しについてお伝え致しましたが、
先日、コテ塗り、噴付による外装が完了しました。

2階エリアを黒く塗装することにより奥行きが強調されシンプルなフォルムが一層際立ちましたね。
玄関廻りは塗り壁。

ザラザラのテクスチャーが、味わい深い風合いを作ってくれます。
この塗り壁、様々な塗りパターンがあるのですが、程よいフラットさを醸し出すこのパターンがしっくりきますね。
個人的には、ムラができるパターンも見てみたい気がしますが。
次に、内部です。
クロスが全面貼り終わり、白く明るい室内へ変貌を遂げておりました。


新しい姿へ移り変わる度に、現場で一人興奮しているワタクシ。
その脇で、淡々と木製建具の取付を行っている建具屋さん。

なかなかの温度差(笑)
次回は、内部を見て回りたいと思います。
「大平賀の家」木を活かす手仕事、本物の素材がもつ質感を大切にする。
本日、2投目のアップ。
「大平賀の家」の現場の空気を吸ってきました。
気になる工事過程ですが、木による外装が一段落し、これから塗装へと進むところです。

道路からもこの木質感が目に留まりますので今回は外装の板張りに着目。

仕上げは、軒天、鎧張り共に年輪が際立つ杉。
使用している木材保護塗料は、木の通気性を妨げない他、風合いを保ちますのでしっとりとした安らぎが籠っています。
専務曰く、コストに制約があることを感じさせない仕上がりのためには、
納まりの他に素材そのものの良さを引き出す工夫を凝らすことが大事なんだそう。
なるほど。
それは、この玄関廻りをみて分かる気がする。
あれ?
サッシがいつものアルミ樹脂じゃない?
フフ。
「上川辺の家」既存設備機器か造作+設備機器か。
3月より「上川辺の家」の見所をお伝えして参りましたが、ラストは既存設備機器について取り上げてみたいと思います。
弊社は、無垢の木を取り扱う建築会社で、自社設計の造作、造作家具には特に力を注いでおります。
その為、建物のあらゆる部位が、大工さんによる手仕事によって施工されるわけですが、ゴリ押ししているわけではありません。
無垢のシャレオツな造作はしたものの、メンテナンスやコストの面から日常の負担になっては本末転倒。
肝心なことは、やはり「そのご家族にとって心地よい暮らし」だと専務は考えているようです。
「上川辺の家」でも設備機器は全て既存品を選んでいただいております。


キッチン、バスルームは、「上川辺の家」のみならず殆ど既存品の施工をしております。
各メーカー様とのお付き合いも深いので、最新設備機器や特徴など有効なアドバイスが出来ると思います。
以下、既存設備機器の事例です。
キッチン。


バスルーム。
・
・
・
・
・
造作ばかり撮っていて画像がなかった。
物凄く偏ってますね(苦笑)
設備機器、次回から目を向けたいと思います。
以上、「上川辺の家」の見所でした。
A様、竣工おめでとうございました!
そして、真摯にご協力くださった協力会社の皆様、本当にありがとうございました!
「上川辺の家」インナーバルコニー
住居を新築するにあったって脇役的存在の部類に入るバルコニーですが、南面、つまりファザードに位置することが多いですよね。
となると、住環境の充実度は勿論、町の景観づくりにも関わってきます。


「上川辺の家」では、インナーバルコニーを採用し、西日を和らげ外気に触れても綺麗に保てるよう配慮しております。
撮影日までに木ルーバーが間に合いませんでしたが、通風・目隠し・バルコニーの意匠としてルーバーを設けることが多いです。

床は、FRP防水2プライ工法。
ガラスマットを2枚張りする工法により入念な防水処理を施します。
味気ないんですが、水は排水管へ流れ込み高い防水効果を発揮!
家のタメには最適です。