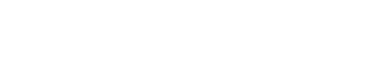blog
Writer/Maya 事務・CADオペレーター
「建築」や「モノづくり」の最前線に立ち、設計者の価値観に基づいた機能的及び情緒的な価値をお伝えできればと存じます。
「藤倉の薪ストーブのある平屋」ハードな作業もOK!多目的土間空間
藤倉の薪ストーブのある平屋、最後は、この家ならではの特別仕様に注目してみようと思います。
家づくりの過程を楽しみ、建築が竣工した後は、新しい生活が待ち受けています。
その日常生活は、各ご家庭により異なるため、やはり各々のご家庭にあった間取りや動線を検討することが望ましい。
そういったお考えの方が注文住宅を選択されるわけですが、
この家では、そういったU様ならではのライフスタイルを汲み取り、土間の多目的家事室を設けました。

U様のルーティン作業に必要な道具は、洗濯機、洗い場、勝手口、室内物干し(後付)など。
床が土間ですと、仕事着や靴洗い、野菜洗いなどランドリーに留まらずハードな使い方も許容してくれます。
ちょっとぐらい床が泥で汚れても、水で流せばOK!
勿論、ルーティンは移動距離を少なく。


水周りは集中させ、連携できるよう利便性を図っています。


家事で感じるストレスや負担を軽減し、気持ちをラフに。
ヒアリングでは、是非、現状のお悩みやご不満をはき出してみてください。
自分たちならではの間取りや動線がみえてくることでしょう。
以上、「藤倉の薪ストーブのある平屋」のご紹介でした。
わたくしも建築図面に携わる身として、一棟一棟思い入れが深く、世にお伝えしたい気持ちが非常に強いです。
図面作業や現場が優先となりますので時間はかかりますが、これまでご一読いただいてありがとうございます。
次回からは、「那加の平屋」をお伝えしたいと思います。
同じ平屋でも周辺環境、敷地、ライフスタイル、嗜好などありとあらゆることが異なるため、
「藤倉の薪ストーブのある平屋」とは性質の違うお住まいです。
お時間がございましたら、是非ご一読ください。
「藤倉の薪ストーブのある平屋」自然を引き寄せる半屋外空間
本日、少し時間が出来ましたので、藤倉のご紹介の続きを書いていきたいと思います。
藤倉の特徴4つ目は、半屋外空間として設けた「木製テラス」です。
高気密・高断熱、24時間換気、全館空調。
新築を検討するうえで、室内の温熱環境は心身の健康と深く結びつくため、これらのスペックをあげていくことは必然となりますが、
外部の環境が良好な場合、その環境を暮らしに取り入れたくはありませんか?
実際、そういった自然志向のOB様は大変多くいらっしゃり、
ヒアリングでも、「自然に身を委ねたい」「季節の流れを感じたい」「風景を愉しみたい」とのお声をよく耳にします。
自然の恵みに預かることは、我々も大賛成で、積極的に屋外空間の居場所を造作しております。
この藤倉の地は、ご覧の通り、自然の恵みを五感で受け止めることができる場所。

あぁ、視界が開けているって気持ちいい。
この環境を単に眺めることに留まらず・・・

LDKと隣接したテラスを設けることで、室内外が連続した印象に仕上げています。
すると、どうでしょう。


庭に張り出した大きなテラスと室内が一体となり、まるで外の自然を室内に呼び込んでいるかのようではないですか?
窓辺ではなくとも、どの場所にいても、外の自然に引き寄せられます。

そこに窓があると開けたくなるし、テラスがあれば自然と外に出たくなる。
自然愛は行動にあらわれますね。


因みに、こちらの4連テラス窓の開け方は斬新です。笑

専務曰く、自然の力は強く、心地良い室内であっても気持ちは外へと向かう。
自然には、そんな吸引力があると思っているそう。

本来、自然の脅威から身を守るための家ですが、反対に、自然の恵みに向かって設計することも大切だな、と。
わたくしも、ここに座っているとそう実感できます。
「藤倉の薪ストーブのある平屋」アンティーク仕上げ
続きまして・・・
藤倉の平屋は、計画当初から「アンティークっぽい内装」が念頭にあり、
この曖昧でおぼろげなご要望を設計者である専務がどう解釈したかをお伝えしたいと思います。
皆様は、アンティークと聞いてどんなイメージを抱かれますか?
わたくしはシンプルに「骨董品」「100年以上の歴史がある価値の高いもの」「DIYによるカフェスタイル」といったところでしょうか。
アンティークに限らず、脳内イメージは人によって異なるため、専務がどう調理するのか秘かにとても楽しみにしておりました。
さて、その手法ですが・・・
今回、年代物の古材は一切使用せず、新品の素材の力を借りて「ほどよい味わい」をメイキングしております。

まず、木材ですが、
この家ではエイジング加工を施した無垢フローリングや食品衛生法に適合した塗料で着色した無垢天井や建具など
コストバランスや機能を考慮したうえで構成しています。


次に、石材。
石材の特徴は、産地が同じであっても不均一で、ひとつとして同じ表情をもっているものはないこと。
これらのタイルは「ほどよいこなれ感」を醸し出してくれます。




また、ひとつひとつの面に材の違いはあってもそれらが集合すると均一性がでるよう気を配っています。
一見別物のタイルですが、両者は同じアンティーク感を目指しているのですね。


仕上げ材選択の判断基準は多岐に渡りますが、
専務曰く、全ての材料に均一性をもたせることで住空間の魅力が一層引き立つと考えているそう。

心地良さは、個人の感覚に左右されます。
精神的な拠り所として、あなたはどんな仕上げを選ばれますか・・・?
「藤倉の薪ストーブのある平屋」オープンキッチンの立ち位置
少し間が空いてしまいましたが・・・
お次は、これまで事例のなかったフレームキッチンを取り入れたオープンキッチンをご紹介したいと思います。
近年、家族間のコミュニケーションを重視するご家族や、生活を彩るデザイン性の高いキッチン及び調理器具が増え、
お客様も「キッチンをみせること」に抵抗がなくなってきているようで、弊社の事例でもオープンキッチンが増えてまいりました。




しかし、オープンキッチンにするにはそれなりの勇気が必要であり、それを提案する我々も裁量が問われると考えています。
藤倉の平屋でも、奥様のご要望でオープンキッチンを採用。
それも引き出しは無く、鉄のフレームのみで構成されたフレームキッチンです。

収納は、ディスプレイ感覚。


全てが見えるため置くものに配慮したいところ。
この課題はU様に委ねるとして、我々が配慮しているのは「キッチンぽく見せない工夫」です。
最近のレンジフードやコンロ、水洗は、各社デザインものが多く家具のようにみせることは容易いのですが、
問題は、冷蔵庫や吊戸棚など大型のもの。
これらは、最もキッチンぽさがあらわれるため、打合せ時にどこまでこだわるか話し合う必要があります。
この家の場合は、壁を利用して冷蔵庫を隠し、バックカウンターをLDK空間に合わせトータルプロデュース。
(向かって左の窪みが冷蔵庫置き場となります。)

我々は、キッチンがそのご家族にとってどんな立ち位置なのか考慮し、
オープンの場合は、常に目に晒されることを意識しながら造作しています。
近年、キッチンが「調理そのもの」から「ご家族との会話」「お子様の見守り」「食を中心とした生活」に変化しつつあるので、
オープンキッチンの注目度が高いのも納得ですね。

そのご家庭に合った使いやすいキッチンにするために、
キッチン本来の機能性能のほか立ち位置を考慮してバランスを図っていきたいところです。
「藤倉の薪ストーブのある平屋」上質におごることなくひっそり佇む
本日より、2月にOPENHOUSEをさせていただいた「藤倉の薪ストーブのある平屋」と
3月竣工の「那加の平屋」の特徴をお伝えしたいと思います。
まず「藤倉」から。
「藤倉」と申しますと、美濃加茂在住の方は聞きなれない地名かもしれませんが、
旧伊自良村のあたりで、田園と里山に恵まれた自然豊かで静かな集落になります。

そのため、こちらの建築は、周囲の山並みや一面の田園風景を汲み取り、
悠久の時間が流れる日常となるよう薪ストーブや和情緒、ご要望だったアンティークを取り入れた平屋のお住まいといたしました。
外観は、自然豊かなこの地では「厚化粧をせずひっそり佇むことが相応しい」との考えから本物素材の質感を多用し、
特に、ファザードは、三角屋根のシンプル形状にすることで「静」の表情を創造しています。

得意気に佇むのではなくひっそりと。
塗り壁の外壁は、そのような静のニュアンスづくりにも打ってつけ。
人工のサイディングボードでは均一すぎるのです・・・。
シミュレーションで試行錯誤した甲斐がありました。


南より。
実は、奥行きがかなり深い。

晴れの日。
テラスと軒天は自然との繋がりをもたせるため無垢材で。

南より。
たちを低くしているため直線的なフォルムが際立ちます。

OPENHOUSEの際、弊社は「直線的な形状が多い」とのご意見をいただきましたが、
それは、曲線を多用する西洋の建築に対し日本建築では水平垂直の直線美が定着しているからです。
これは、石材はアール加工がしやすく、木材は直線的な加工がしやすいため。
弊社は、伝統建築を取り入れた設計を得意としており、若い世代にも繋げたい想いから、このような直線的なフォルムが多くなります。
また、実は、ご予算に対する戦略でもあり、専務の心持ちが反映されています。
以上、外観のご紹介でした。
「則武の家」地鎮祭
新しい現場です。

建築地は、岐阜市則武。
教育・医療・飲食店が充実した住宅街の一画です。
先日、地鎮祭を執り行い・・・


現在、基礎工事の段取り中です。
さて、こちらの住宅は、南北に長い75坪の敷地に15帖分の吹抜けのある二階建てを計画しています。
プライバシーを重視した外構構成なので、吹抜けからたっぷりの陽光を取り込みます。
今日まで度々事務所へご足労いただきお打合せを重ねてきました。
上棟が待ち遠しいことでしょうがもう少々お待ちくださいませ。
「室原の薪ストーブのある平屋」竣工おめでとうございます
昨年秋口より工事を進めてまいりました「室原の薪ストーブのある平屋」。
およそ6ヶ月に及ぶ工期を経て無事竣工いたしました。

自然素材で満たされた穏やかな土間空間。
伝統建築を間宮建築風にアレンジし随所に設えています。

こちらに住まうご予定のN様ご一家には、N様のご両親にも大変お世話になりました。
ご一家揃って工事をそっと見守っていただき大変感謝しております。
土間のある山間の暮らし。
必見です。
順次、特徴をお伝えいたしますね。
「建築日誌」長源寺様お手洗い改修
弊社は、幅広い世代のお客様にご愛顧いただいておりますが、
それは、社長が現役で、シニア世代のニーズにもお応えすることが可能だからです。
シニア世代のお客様のご依頼は、改築や増築が主。
神社や公民館の雨漏り修繕、地域の民家のリノベーションやガレージ造設など工事内容は多岐に渡りますが、
今回、関市「長源寺」様より、ご参拝者様用の外部トイレ改修のご依頼をお受けいたしましたのでレポしたいと思います。
社長が、専任で設計、施工管理を担います。
こちらが、該当の外部トイレ。


約30年以上前に建てられたものだとか。
ブロック積の構造で昔懐かしい味わいを感じますが、後方の築約20年の本堂とはミスマッチ。
木造に一新いたします。
内部です。


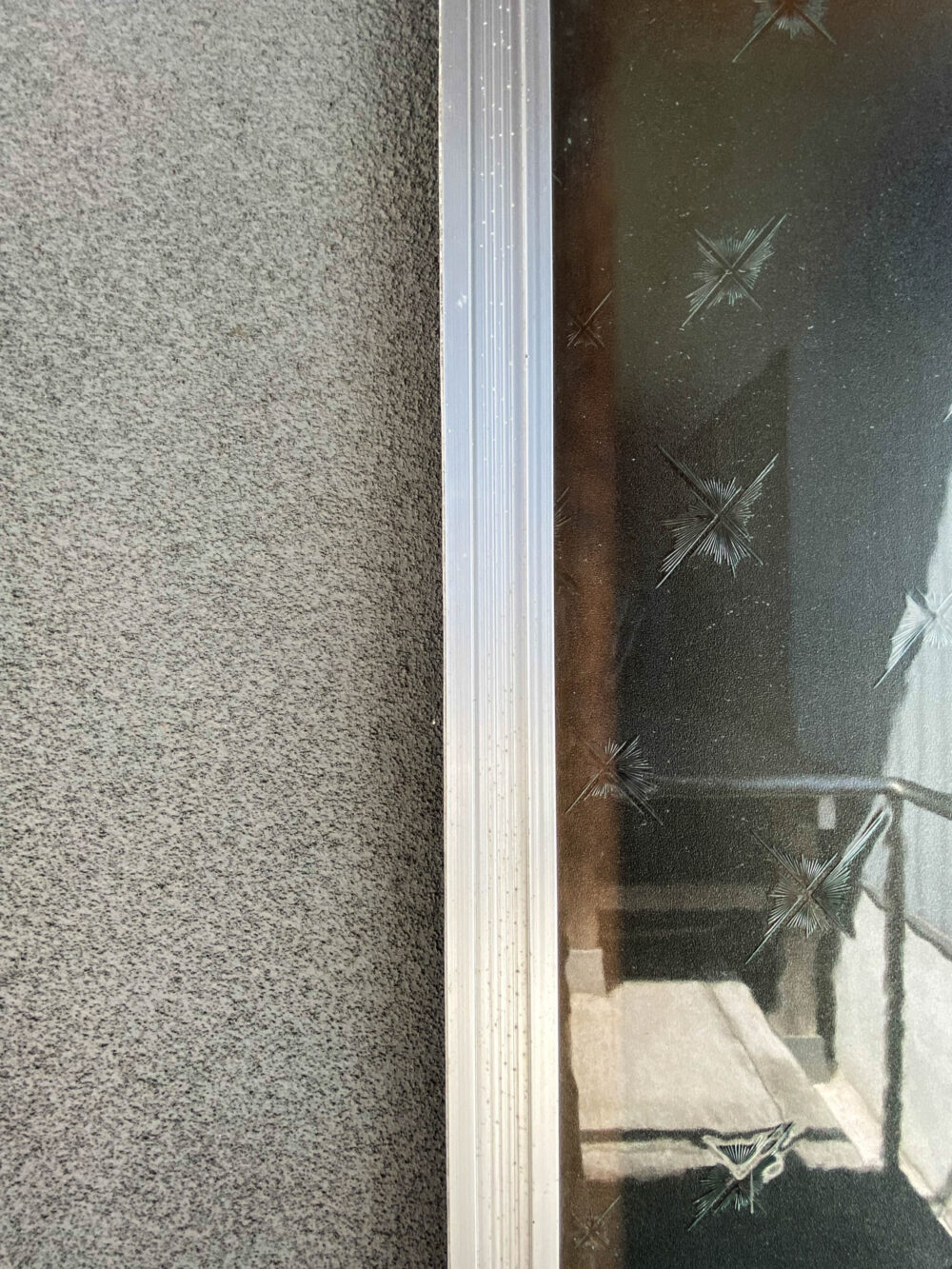
レトロな星模様のアルミサッシを開けると、これまた年代物のタイル貼りが。
ちょうど我々世代が幼少の頃のデザインなので懐かしさに包まれます。
しかし、経年劣化した洗面台、段差、男女混合、採光など現代の視点からすると気になる点も多数。
今回は、リノベーションではなく改築。
これまで何十年とお世話になった部材達に敬意を示しつつ、上記の気になる点を改善し、
地域の皆様の誰もが心地良く使用できるよう改新させていただきます。
工事は4月下旬スタート。
またレポいたします。
「加茂野の長期優良住宅」上棟おめでとうございます
先々週のとある日。
弊社事務所のご近所さんである「加茂野の長期優良住宅」の上棟をおこないました。

現場は、畑を営む民家が点在する静かな環境で、敷地はなんと約120坪。
自然の多い加茂野ではゆとりある土地に恵まれておりますが、その中でも広大な部類です。
そのため、敷地を持て余すことなくプラスの要因を引き出して生活を豊かにしたいところです。
さて、毎度お馴染み建方の様子です。




太い梁が見えている部分はお車2台分のガレージですが、
母屋の玄関と連結しているので間口は10mに及びます。
3台分のガレージを造作させていただいた「下米田の平屋」と同等の規模。
充実したカーライフのお役に立てればと願います。
こちらはファザード。
ガレージ内に玄関が存在します。

実は、敷地いっぱい活用しているため奥行きも深い。


延床面積約50坪のボリュームのある平屋のお住まいです。
平屋の場合、広ければ必ず快適というわけでもなく、中心部分は光や風が届かず暗くなりがち。
敷地が広大な分、採光通風には特に気を配っておりますので、今後のレポではそのあたりも着目したいと思います。
それでは、H様上棟おめでとうございました。
工事関係者の皆様、ありがとうございました。
「那加の平屋」お引渡し時の儀礼
先週のとある日。
「那加の平屋」が竣工し、無事お引渡しをさせていただきました。

そこで、今回は、儀礼の様子をピックアップ。
昔から続く伝統的なならわしとして、木造軸組では、地鎮祭と上棟式の二度、神様にご挨拶をする機会があります。
これは、地を慎め、工事の安全、家の繁栄、ご守護などを祈願するもので、
信仰心が薄れた現代でも、建築現場では、持統天皇の時代から続く古式の神祭りが行われています。
地鎮祭は、お客様の宗教観に合わせた儀式を執り行っておりますが、
上棟時の儀礼は、断熱材の特性上、執り行っておりません。
そのため、弊社では、竣工時に棟札など一式を小屋裏に納めさせていただきます。


今回も、専務が必要なお品をかごに入れ、

家の守り神様として大切に納めさせていただきました。
因みに、飾り物一式は弊社がご用意いたします。
その後は、窓や設備機器のご説明をさせていただき、
本キーや取説、図面一式などをお渡しいたします。






近年設備機器のハイテク化が進み、様々な便利機能が盛りだくさん。
現場でのご説明は簡潔なので、お忙しいとは思いますが取説を熟読して使いこなしてくださいね。
以上、お引き渡しの様子でした。
後日、画像処理が終わりましたら、この家の特徴をお伝えしたいと思います。
乞うご期待。