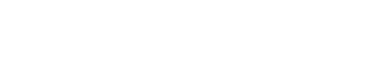blog
Writer/Maya 事務・CADオペレーター
「建築」や「モノづくり」の最前線に立ち、設計者の価値観に基づいた機能的及び情緒的な価値をお伝えできればと存じます。
「建築日誌」神社の拝殿修繕
神社の拝殿の老朽化が進んだため修繕工事を行っています。
仁徳天皇のお祀りがされている神社です。

長い参道の先に不浄なものの侵入を防ぐために造られたとされる蕃塀があり、
その奥にこちらの拝殿が建てられています。

屋根や外壁が崩れ、参拝者にとって危険な状態でした。
参拝者が安全に参拝できるよう梁から立て直します。
「加治田のリノベーション」木造住宅の一部を再構築
現在リノベーション中の富加の現場より。
築40年以上になる木造住宅の一部を再構築しています。
こちらは、当時の職人の技が光る外観。


近代化されていく時代の雰囲気も併せ持つ古き良き木造住宅ですね。
リノベーションは包括的に改修を行い資産価値を高めるわけですが、
今回は、断熱性能の改善、間取りと内装の刷新、一部外装の改修などを計画しております。
現在は、断熱材の設置が完了し、無垢フローリングを張っているところ。


築40年以上ということで、この家には、土間やレトロな素材や中庭など様々なお宝が存在します。
長年関わってきたものとこれから関わるものが混じり合い、この空間にも愛着が生まれてほしいと願います。
「建築日誌」無駄がなく合理的
ガルバの殻に包まれる前の基礎屋さんの事務所です。

1階に駐車場2台分、2階に事務所を構えたコンパクトオフィス。
外観、間取り、設備・・・全てにおいて無駄がなく合理的。
かかるコストに対し効果を存分に上げています。
「建築日誌」事務所の上棟
先日、美濃加茂市下米田町にて、
かねてより計画を進めてまいりました新築の事務所が無事上棟いたしました。

インナーガレージ2台分を確保した2階建ての事務所です。
弊社では、住宅以外にも小規模経営の店舗や施設、事務所など様々なご依頼にお応えしております。
ブログ停滞期には、就労継続支援事務所「スマイルサポート」様の宿泊施設を改築。


働く環境がより整備されることで、
円滑なコミュニケーションや組織の活性化が更に向上することを願います。
こういった施設や事務所の建築は、住宅と切り口が異なるため我々も勉強になります。
今後も多様なニーズに応えていきたいところです。
それでは、T様、上棟おめでとうございました!
今後ともよろしくお願いいたします。
「建築日誌」プチリノベの参考にどうぞ
弊社のプチリノベ、着々と捗っております。
小さな工事ですが、撮り溜まった画像を公開。
プチリノベの参考にどうぞ。
昭和時代の一般的な子供部屋からスタート。

左から、無垢フローリング張り、壁の一部撤去、書類棚造作。
フローリングはウォールナット、造作も同色で仕上げます。



続いて、パテ処理、天然塗り壁材コテ塗り、仕上がり。
今回のリノベはローコストで。



壁の色をこの色にした理由は、そこにあったから。
建築屋あるあるです。苦笑

しかし、現状の事務室と調和のとれた空間になりそうです。
あとはオーダー中の木製建具を取り付けたら完成です。
またレポいたします。
「建築日誌」事務所パンク
7、8年前に、家の古い離れをリノベーションした弊社事務所。

この度、書類や図面の増加により事務室が窮屈になったため、
お隣の部屋との間仕切りを無くし、事務室を広くする運びとなりました。
迫りくる書類群。

因みに、もう一ヶ所の壁面からも大群が迫ってきます。苦笑
こちらがお隣の部屋。


この部屋は、元々専務の部屋だったのですが、現在は冷蔵庫を置いたり食品庫として使用しておりました。
左は解体、右はフローリング下地を整えたところです。
六畳一間の一般的な子供部屋のつくりですが、建具が渋い味を出しています。
今は亡き建具職人による木製擦りガラス戸。

約30年前の代物で、丁寧に組み込まれた装飾がお見事です。
今まで我々のために働き続けてきた健気な存在で、経年による傷やガラガラ音など全てが愛おしい。
また、この建具から想うこと。
無垢の木の傷や経年変化を味わいと捉え、調子が悪くなったらメンテナンスをし、愛着を感じていただく。
間宮建築の造作の目指すところでもあります。
加えて、子へ孫へ受け継いでいただけたら申し分ないのですが、
時代や暮らしの変化によるニーズによりこの願いを叶えることは中々難しいのが現状。
この建具も、今回のリノベーションのニーズに合わないため引退いたしますが、
我々は、今後も、世代を超え受け継いでいただくことを前提としてモノヅクリに励む次第です。

今回のリノベは簡単な工事ですが、
せっかくなので小規模のリノベーション事例として記録していきますね。
「建築日誌」長源寺様木造公衆トイレ
2021年8月竣工「長源寺様公衆トイレ」。
社長が設計・施工管理を担当しました在来工法による木造建築です。

公衆トイレは、利用者数、予算などから一般トイレとし、本堂、境内、駐車場からアクセス可能で、
訪問者が心地良く利用できるようバリアフリー化に努めています。
外観は、耐朽性に優れるヒノキを使用。
これは、将来、経年変色した際、周囲の建築物に寄り添って欲しい想いを込めています。
また、境内の建築物に合わせ真壁工法を取り入れ、本堂の格式と遜色のない意匠を意識しています。


また、内外部共に段差、手摺、清掃のし易さに拘り、利用上の便を考慮。

特に、社長自ら製作したささらげた階段は、お年寄りやお子様の利便を考慮し、通常より低い蹴上げとしています。


内部は当初、男女共用で、設備的にも古く老朽化がみられましたが、利便、安全、衛生面の視点から快適性を改善し、
自然光を大きく取り入れながらも、ヒノキの艶と香りを感じられる落ち着いた雰囲気に仕上げています。




是非、美しい木肌をご堪能ください。

社長曰く、今後もこうやって、近年の技術進歩を加味しながらも施工の原点に立ち返る建築を残していきたい。
今後もご依頼があれば、目的に応じた建築環境を整えていきたいとのことです。
「建築日誌」市橋の平屋上棟
数年前、新築のご依頼をお受けした市橋の家。
今回、そのお施主様のご両親の新築依頼をお受けし、先週上棟いたしました。

「稲辺の建替」もそうですが、多世代に渡りご依頼をいただくことは、
地場工務店にとって一番の基である信頼性をご評価いただいているようで、大変光栄に存じます。
信頼というものは、一朝一夕には得られず、
これまで一棟一棟丹念に向き合ってきた証として受け止め、心の糧にいたします。
この家は「稲辺の建替」同様、これからシニア世代を迎えるご夫婦のための住宅で、普段の建築と趣旨が異なります。
性能に重点を置いているため、工業製品の割合の高い住宅となる予定。

これは、チャレンジ精神を重んじる我々にとって有意義なコンセプトであり、
視野を広げる機会を授けてくださりありがとうございます。
それでは、M様、上棟おめでとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
「建築日誌」長源寺様、竣工おめでとうございます。
先日、約3ヶ月の工期を経て、長源寺様の外部トイレが無事竣工を迎えました。
久方ぶりのヒノキ建築。
随所に匠の技が生きています。

加茂野のOPENHOUSE後に、社長の想いとともに特徴をお伝えしたいと思います。
「建築日誌」長源寺様、手刻み階段
とある日の自社工場の一コマ。

社長が手掛けているのは、ささらげた階段の製作です。
ささらは山切りカットの土台で、その上に踏板を組んだ階段といえばイメージしやすいでしょうか。

階段は、手刻み。
社長曰く・・・
「経験の乏しい人間がやると傷がつくが、若かりし頃、拝殿建築を厳しく仕込まれたからその経験が生きている。」
とのこと。
因みに、こちらは、ベニヤ板に描かれた原寸図。
手刻みの場合は、手数がかからないよう原寸図から寸法をあたり製作します。

手刻みによる施工もそうですが、伝統技術を用いる職人が減少している現代。
社長曰く、自身の腕や知識は、2代目である専務に99%伝承済みとのこと。
あとの1%は・・・
気になる方は、今度わたくしに聞いてみてください。笑